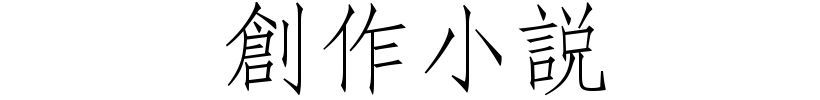時は中世、場所は、ヨーロッパ。
石造りの城の中で、戴冠式が執り行われている。床には、青の絨緞が敷き詰められている。
ビショップが、キングとなるべき人物に、剣を渡す。キングとなるべき人物は、受け取った剣を、祭壇に捧げた。こうして、剣の役目は終わった。
本来は、戦いの場で、血の雨を降らすはずであった、剣は、不満のあまり、ゴトリと音を立てて転がり、床に落ちた。
そうする資格が、この剣にはあった。この剣は、生きている間から、その神業的技術故に、伝説となった、職人の手になるものだった。
その職人は、思想を持っていた。剣は、人を殺すためにある。だから、職人は、戴冠式で使われる、剣を作る時も、その殺傷能力を最大限にするように作った。そして、この剣は、職人が作った中でも、最高のできだった。
剣が、不満を洩らしたのももっともだったのだ。
しかし、そのために、剣は、不吉なものと見做されてしまい、地下室の奥にしまわれてしまった。
時は、流れる。ここは、東京。
ルイは、迷路のような、街を歩いている。
ルイの肌は、白く透明だ。ルイは、けっして太陽の光りの中では歩かない。ルイを照らすのは、月か星だけだ。
ルイは、なにかに呼ばれたような気がした。見回すと、小さな、古ぼけた、アンティック店があった。ルイは、店の中に入った。ボロボロになった鞘に収められた、剣が吊るしてあった。ルイは、自分を呼んだものが、この剣であることをすぐに悟った。
剣に見入る、ルイに、店番の老爺が、歯のない口を見せて笑いながら言った。そなたに進ぜよう。誰も、その剣を鞘から抜くことのできる者は、いない。店に置いておいても、一文の価値もない。
こうして、剣は、ルイの手の中に納まった。
ルイは、柄に手を掛けてみた。剣は、鞘から、躍り出た。剣は、夜道の中で、新月だというのに、青白く輝いた。
ルイは、自分が求めているものと、剣が求めているものが、同じものであることを知り、ニッコリと笑った。
1995/05/13